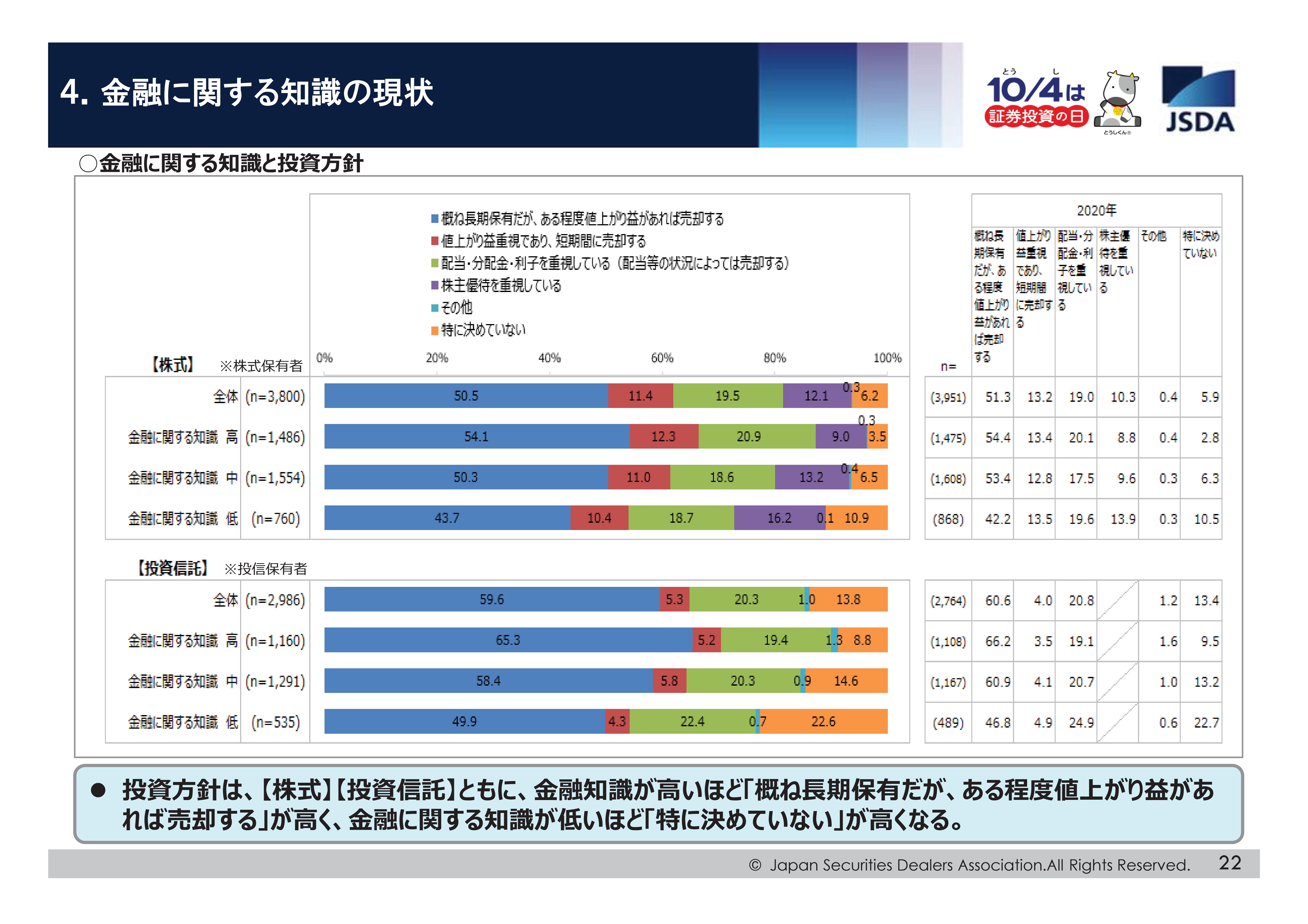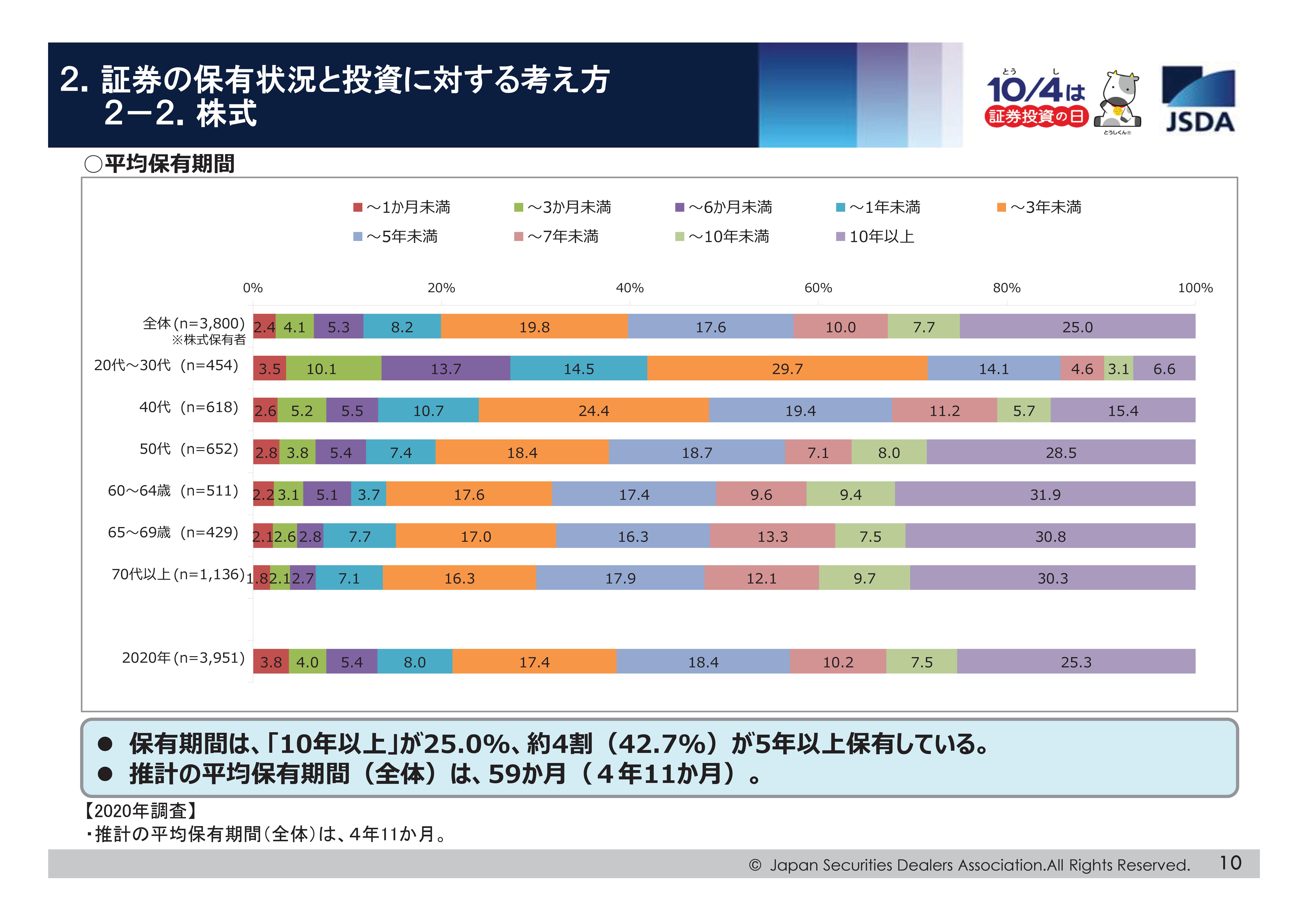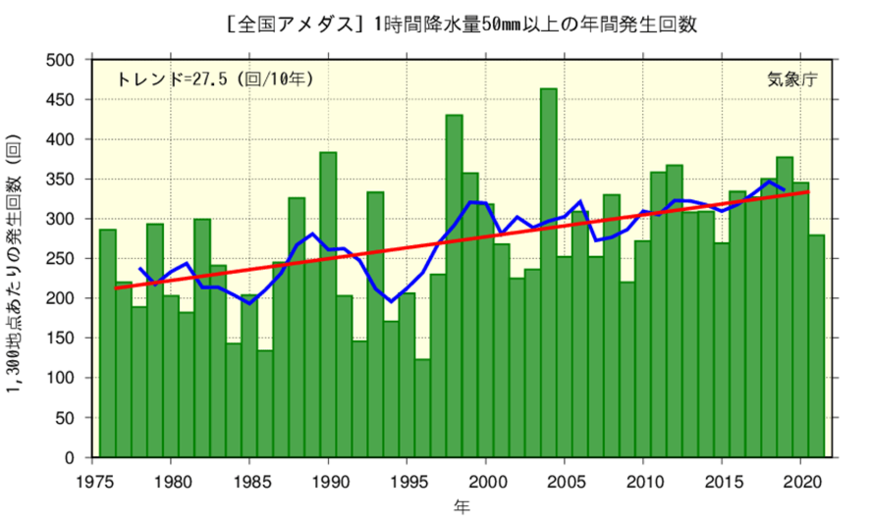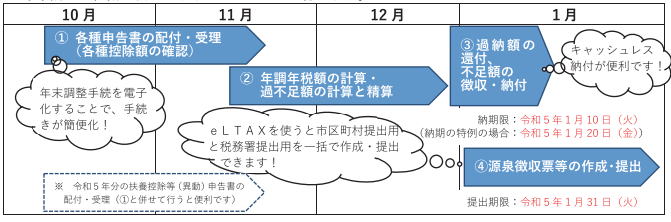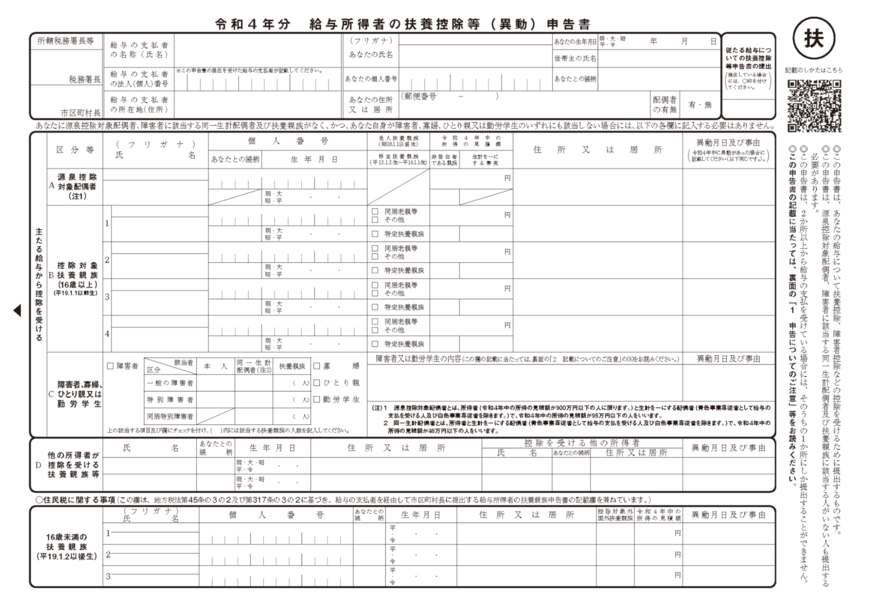Posts Tagged ‘中西康修’
投資トラブルや運用の失敗をしない為には?
8月が終わり、朝晩が真夏に比べると幾分か過ごしやすい今日この頃
季節的にも外に出る機会も増え、夏のアクティブな雰囲気のまま、羽目を外す事もありますが、こんな時こそ体調を崩す原因になったりもしますので、きっちりと自己管理をしておきましょう。
それは、「お金」についても同様です。
最近では芸能界における投資トラブルが注目を集めていますね。
また消費者トラブルも高齢者だけでなく若い世代にも事案が後を絶ちません。
そこで今回は、自分の身を守るために必要な「金融リテラシー」に着目し、日本人のリテラシーの実態と紐づけながら「資産運用で失敗する人」の行動3選を紹介します。
投資信託についても同様のことが言え、金融知識が高い人で長期保有をする人は65.3%、方針を決めていない人は8.8%であるのに対し、金融知識が低い人で長期保有をする人は49.9%、方針を決めていない人は22.6%となりました。
これまで色々な方の人の投資相談に乗ってきましたが、計画性の無さはストレス耐性の低さにつながる印象があります。
「短期・中期・長期のどのタイミングでパフォーマンスがプラスになっていればよいか」を考えず、なんとなく株や投資信託を買って損が生じた際、どのように次のアクションを考えていいかがわからなくなることは多いでしょう。
これは、リターンが生じた時も同様です。
長期投資志向ではないうえに計画性がない場合、短期的な値動きに気持ちが振り回された結果、売り時がわからず、利益が減ったり損失が拡大したりする可能性は高くなってしまうでしょう。
突然の豪雨や異常気象 おうちの保険は?
今年も暑い夏となりそうです。
夏になると毎年、異常気象による災害ニュースがありますが、特にゲリラ豪雨と呼ばれる『線状降水帯』の特別警報は気を付けておかなければなりません。
今回は皆さんのお家に対しての保障の代表例『火災保険』について載せておきます。
私達の暮らしを支える保険の一つ、火災保険は「火事になったときに保険がおりるもの」と思われる方も多いですが、実は火災保険がカバーするのは火事だけではありません。
先述の増加するゲリラ豪雨にも役立つかもしれないのです。
ゲリラ豪雨とは局地的に大雨が降ることで、全国どこでも発生する可能性があります。気象庁によると、1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加傾向にあります。
災害に備えることは必要ですが、補償を知ることも大切です。火災保険がカバーする自然災害について知っておきましょう。
不妊治療 保険適用 制度の概要
2022年4月1日、ついに不妊治療の一部に保険が適用されました。
これまで不妊治療は健康保険の適用外だったため、不妊に悩むカップルにとって経済的負担は計り知れないものでした。今回の保険適用により、負担が軽減されることとなるでしょう。
一方で、不妊治療の保険適用には気をつけたいポイントが2つあります。制度の概要を押さえるとともに、保険適用にかかる注意点をまとめてみました。
1. 不妊治療が保険適用となった背景
これまでの不妊治療でも「治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性・安全性等が確立しているもの」には保険が適用されていましたが、原因が不明であるものについては自己負担となっていました。
しかし不妊治療では時に数十万円という高額な負担がのしかかることも多く、保険適用を望む声が強まっていたのです。
さまざまな議論を経て、2022年4月1日に保険が適用されることとなりました。
2. 不妊治療に保険が適用される条件とは
すべての不妊治療に保険が適用されるわけではなく、条件があります。
2.1 不妊治療の種類
- 人工授精
- 顕微授精
- 体外受精
- 体外受精などで得た受精卵の培養
- 胚の凍結保存
- 胚を体内に戻す胚移植
2.2 不妊治療を受ける女性の年齢及び治療の回数
上記の不妊治療のうち、2から5は治療が始まる時点で女性が43未満であることが条件です。
また体外受精のうち上記の6では、保険適用となる「胚移植の回数」が決まっています。女性の年齢が40歳未満では子供1人につき6回、40歳以上43歳未満では3回まで保険が適用されます。
2.3 不妊治療を受ける男性の年齢
男性の場合、年齢制限はありません。また男性に行われる検査にも保険が適用されます。
2.4 不妊治療を受けるカップルの関係性
事実婚であっても保険適用の対象となります。
3. 「不妊治療が保険適用」気をつけたい注意点
一見、不妊治療が保険適用になるのは大きなメリットに思えます。しかし今回の保険適用では、注意したいポイントが2つあります。
3.1 助成金廃止で自己負担が増えるケースがある
これまでは体外受精や顕微授精などの特定不妊治療と呼ばれる治療に対し、最大30万円を支給する助成金制度がありました。
助成金制度は保険適用開始と同時に廃止されるため、治療費によっては保険適用後の自己負担が上回ることもあるのです。
ただし経過措置として、年度をまたぐ1回の治療については助成金が支払われます。
3.2 保険適用されるのはガイドラインで推奨される治療のみ
すべての不妊治療に保険が適用されるわけではありません。一般社団法人日本生殖医学会のガイドラインにて実施を推奨しているもののみが対象です。
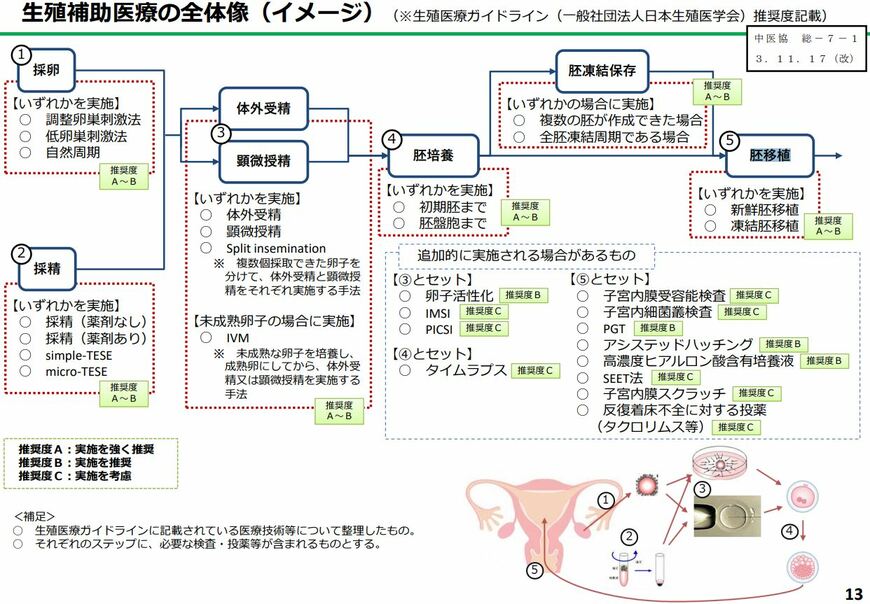
厚生労働省 先進医療における不妊治療の対応について
保険適用となるのは、ガイドラインの推奨度A・B・Cのうち、AとBに該当する治療です。推奨度Cの治療(タイムラプスなど)を実施する場合は、全額自己負担となるので注意が必要です。
流産などのリスク回避に効果のある着床前診断も、今回の制度では保険適用の対象外となりました。
このように対象外の治療がある点については、今後の課題とされています。さらに先進医療として申請される動きもあるため、そちらを経て保険適用となる可能性もあります。
4. それでも不妊治療の保険適用は大きなメリットが
不妊治療が保険適用になることに対し、手放しで喜ぶわけにはいかない現状があります。しかし、保険が適用されるという動きそのものは大きな前進だと言えるでしょう。
保険が適用になるということは、「高額療養費制度」の対象にもなります。高額療養費制度とは公的医療保険の保障の1つで、「ひと月あたりの医療費の自己負担が一定を超えると、超えた分が返還される」という制度です。
例えば70歳未満で年収500万円の場合、ひと月の医療費の上限は約8万円~9万円に抑えられます。
5. 不妊治療のこれから
不妊治療が保険適用になったことをふまえ、制度の概要や注意点をまとめてきました。
対象となるには細かな条件が残り、回数も定められます。都道府県外へ転院される方もまれではないため、こうした回数のカウント方法には検討の余地が残ります。
他にも制度としての課題は残るため、今後も議論は進むことが予想されます。
GWは如何でしたか?長期連休の前は・・・
先週はGW
暖かくなってくると旅行やレジャーを楽しみたいと思いますが、皆さんはゴールデンウィーク如何でしたか?
GW中は医療機関や行政機関等が休みになったり、GW前後は混雑することもあり「もっと前にやっておけばよかった!」と後悔することもあります。
今回はGW等の大型連休前にやっておきたいことを4つご紹介します。
併せて今年の残りの長期休暇がどれくらいあるのかについても確認しましょう!
今年の2022年のGW(ゴールデンウィーク)はいつからだった?
振り返ると2022年のGWは4月29日(金)~5月5日(木)の間でした。
- 4月29日(金)昭和の日
- 4月30日(土)休日
- 5月1日(日)休日
- 5月2日(月) 平日
- 5月3日(火)憲法記念日
- 5月4日(水)みどりの日
- 5月5日(木)こどもの日
- 5月6日(金)平日
- 5月7日(土)休日
- 5月8日(日)休日
5月2日(月)が平日のため、今年は3連休が2回でした。
5月2日(月)と6日(金)を休みにすれば10連休にすることも可能ですので、そうされた方もいらっしゃったかもしれません。
来年のGW前にやっておきたいこと4選
因みに来年のGW↓
2023年(令和5年)のゴールデンウィークは5連休
- 2023年05月03日(水):憲法記念日
- 2023年05月04日(木):みどりの日
- 2023年05月05日(金):こどもの日
- 2023年05月06日(土)
- 2023年05月07日(日)
2023年(令和5年)のゴールデンウィーク(GW)は、2023年5月3日(水)~2023年5月7日(日)の5連休です。
※2023年4月29日(土)は昭和の日で祝日ですが、土曜日のため振替休日となりません。
2023年5月1日(月)と2023年5月2日(火)の2日間は祝日ではありません。
ゴールデンウィークの5連休まで、2日間の平日を挟みます。
2023年5月1日(月)と2023年5月2日(火)の平日を休みにする場合、
2023年4月29日(土)~2023年5月8日(日)の9連休で大型連休となります。
4月は新生活がはじまることもあり、GWまであっという間です。
長いお休みとなるので、特に医療機関などはGW前後は混雑することも考えられます。
GW前に早めにやっておきたいことをご紹介します。
行政機関での手続き
市役所などの行政機関は、GW中は休みになります。
春は引っ越しで転居届や印鑑登録、児童手当などの手続きをおこなうなど、行政機関に出向かれる方も多いですよね。
手続きや証明書の取得などをする必要がある方は、GW前に済ませておきましょう。平日は開庁していますが、GW前後は混雑することも考えて予定を組みましょう。
病院の受診
基本的にGW期間中は病院も休みです。また、GW明けは混雑することも考えられます。
定期受診をされている方は、GW前に受診をし、薬を貰いに行きましょう。
連休中でも各自治体で休日診療をおこなっている医療機関があります。自治体のHP等にその日の当番病院が掲載されているので、お住まいの地域の休日診療について調べておくと安心でしょう。
金融機関の利用
何かと出費が続くGW。普段はキャッシュレスがメインでも、GW中は現金が必要になる機会が増えますよね。
今はコンビニでATMが利用できるので、出金の心配をする必要もそれほどないでしょう。ただ平日より手数料が高かったり、金融機関によってはシステムメンテナンスを行ったりする場合もあるので事前に確認しましょう。
中には窓口でしか取り扱っていない業務もあるので、余裕を持って確認してくださいね。
ネットショッピングのお届け日
GW中でも基本的にネットで買い物できますが、企業によってはカレンダー通り休んでいる場合もあります。
通常は1~2日で届くものも、1週間以上かかってしまう場合も。そうすると「GWで使いたかったのに間に合わなかった」という場合もあるでしょう。
ネットでの買い物は早めにしたり、お届け予定日を確認しておきましょう。
今年の9月の連休&年末年始休暇はどれくらい?
GWが終われば、今年の長期休暇は9月と年末年始ですね。
2022年のシルバーウィークを確認しましょう。
- 9月17日(土) 休日
- 9月18日(日) 休日
- 9月19日(月) 敬老の日
- 9月20日(火) 平日
- 9月21日(水) 平日
- 9月22日(木) 平日
- 9月23日(金) 秋分の日
- 9月24日(土) 休日
- 9月25日(木) 休日
今年は3連休が2回に分かれており、9月は長期休暇になりませんでした。
3日間有給をとれば9連休になりますね。
年末年始はどうでしょうか。
- 12月29日(金) 平日
- 12月30日(土) 休日
- 12月31日(日) 休日
2023年
- 1月1日(月) 三が日
- 1月2日(火) 三が日
- 1月3日(水) 三が日
- 1月4日(木) 平日
年末年始休暇は5日間になります。
有休など工夫次第で長期休暇が取れる方は、久しぶりの休みを楽しみにされた方も多いでしょう。
しかしながらまだまだ、新型コロナウイルスの感染予防対策をおこなう必要はあるので、気を付けながら普段のお休みも楽しみたいものですね。
男性の厚生年金 おひとり様編
お世話になります。新年度になり環境の変わった方もいらっしゃると思います。
それぞれのお立場で、益々のご活躍を祈念しています!
今回は男性おひとりさまシリーズ厚生年金です。
毎月の給与明細を見る度、引かれる「厚生年金保険料」の額に釘付けになる方も多いのではないでしょうか。
給与天引きとして納める年金保険料は、年間にするとかなりの金額になります。
その分しっかり年金を受給できるのか気になりますよね。
とくにおひとりさまの場合、一人分の年金でやりくりすることになります。
そこで今回は、厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、「おひとりさまの男性」が受け取る厚生年金のリアルな金額をさぐってみます。
将来のマネープランを考える上で、一つの目安としてみましょう。
今のシニア男性は「厚生年金」をいくら受給しているのか
厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2021年度末時点で厚生年金を受給したのは1610万133人。そのうち男性は1071万6244人でした。
【男性】厚生年金の受給額(平均月額:16万4742円)
1万円レンジごとの受給権者数は以下の通りです。
- 1万円未満:7万2507人
- 1万円以上~2万円未満:1万2071人
- 2万円以上~3万円未満:5395人
- 3万円以上~4万円未満:1万170人
- 4万円以上~5万円未満:3万714人
- 5万円以上~6万円未満:6万7421人
- 6万円以上~7万円未満:16万3063人
- 7万円以上~8万円未満:24万4810人
- 8万円以上~9万円未満:24万2657人
- 9万円以上~10万円未満:27万3243人
- 10万円以上~11万円未満:35万350人
- 11万円以上~12万円未満:43万8683人
- 12万円以上~13万円未満:51万8659人
- 13万円以上~14万円未満:60万8992人
- 14万円以上~15万円未満:70万4371人
- 15万円以上~16万円未満:79万3583人
- 16万円以上~17万円未満:88万4219人
- 17万円以上~18万円未満:94万8543人
- 18万円以上~19万円未満:94万2288人
- 19万円以上~20万円未満:87万9047人
- 20万円以上~21万円未満:75万7129人
- 21万円以上~22万円未満:59万345人
- 22万円以上~23万円未満:41万4195人
- 23万円以上~24万円未満:28万2665人
- 24万円以上~25万円未満:19万63人
- 25万円以上~26万円未満:12万1426人
- 26万円以上~27万円未満:7万5194人
- 27万円以上~28万円未満:4万4547人
- 28万円以上~29万円未満:2万2741人
- 29万円以上~30万円未満:1万807人
- 30万円以上~:1万6346人
男性の平均は16万4742円で、ボリュームゾーンは17万円以上~18万円未満になっていますね。
その後20万円を超えると、徐々に減少していきます。
おひとりさま男性の場合、上記の収入でやりくりする方が一番多いということです。
【参考】シニア男性は「国民年金」をいくら受給しているのか
公的年金は「厚生年金」の他に「国民年金」もあります。
正確には2階建ての構造となり、「国民年金だけの人」と「国民年金プラス厚生年金の人」に分かれます。
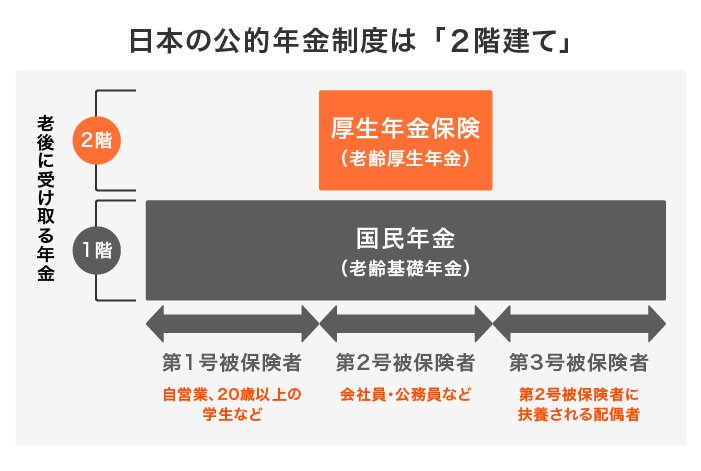
出所:日本年金機構
もし自営業者やフリーランスなどで厚生年金の加入期間がない場合、国民年金のみの受給となります。
ここでは参考までに、国民年金の受給額についても見ていきましょう。
【男性】国民年金の受給額(平均月額:5万9040円)
1万円レンジごとの受給権者数は以下の通りです。
- ~1万円未満:1万2467人
- 1万円~2万円未満:5万8554人
- 2万円~3万円未満:21万6991人
- 3万円~4万円未満:68万1950人
- 4万円~5万円未満:134万1815人
- 5万円~6万円未満:313万9242人
- 6万円~7万円未満:859万4057人
- 7万円以上:40万8917人
平均は5万9040円、ボリュームゾーンは6万円~7万円未満です。
こちらの金額で毎月のやりくりをするのは難しいため、自営業者などはなんらかの方法で自己資金を貯めることになります。
自分の年金額はどう計算する?
おひとりさま男性の場合、受給人数が多いのは厚生年金の人で「17万円以上~18万円未満」、国民年金の人で「6万円~7万円未満」です。
ただしこれはあくまでも今のシニア世代の状況なので、自分の場合にあてはまるとは限りません。
特に厚生年金は現役時代の報酬が大きく影響するため、給料が低い人は年金も低く、給料が高い人は年金も高くなる傾向があります。
そこで自分の年金額を知る方法を3つご紹介します。
毎年送られてくるねんきん定期便をチェック
毎年誕生月には、年金機構からねんきん定期便が送られてきます。50歳以上の方は、こちらに記載された年金額がある程度参考になるでしょう。
ただし50歳未満の場合は、これまでの納付実績に基づいた金額となるため、実際よりもかなり低い数字が記載されています。
ねんきんネットで試算
ねんきんネットにログインすることで、自分自身の年金額をシミュレーションすることもできます。
今後の働き方を変えた場合もシミュレーションできるため、より具体的に知りたい方は試してみるといいでしょう。
自分で計算してみる
年金の受給額には計算式があるため、自分で計算することも不可能ではありません。
ただし計算式はかなり複雑です。
- 65歳未満(特別支給の老齢厚生年金):定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金額
- 65歳以上(老齢厚生年金):報酬比例年金額 + 経過的加算 + 加給年金額
報酬比例の部分は次のように計算します。
- 平成15年3月以前:平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の加入月数
- 平成15年4月以後:平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の加入月数
自分自身で報酬月額を把握できている方は稀なので、自分で計算するのはあまり現実的ではありません。
その他、年金事務所などに問い合わせることで目安額を教えてもらえることもあります。
まとめにかえて
いかがでしたでしょうか。
厚生労働省の公的資料を参考に、おひとりさま男性が受給する厚生年金の月額についてまとめてきました。
ボリュームゾーンが「17万円以上~18万円未満」であることに対し、その印象はさまざまでしょう。
大事なのは「自分なりの目安額を知ること」。
ここをマネープランのスタートラインとし、老後資金の形成に向けて準備を始めてみてはいかがでしょうか。
よく聞く『ゆとりある老後生活資金』の中身って何?
2022年最初の中西ブログです。
改めて、本年も宜しくお願い致します。
昨年秋から先月12月まで食料品の値上げが相次ぎました。
某大手メーカーは2022年3月1日納品分より、ハム・ソーセージ、調理加工食品(麺類除く)を4%~12%、麺類を4%~14%値上げすると公表しました。
頻繁に食卓に出てくる食品の値上げに、お財布事情が厳しい方も多いのではないでしょうか。
特に年金生活となると、相次ぐ値上げは月々の生活費に響きます。
老後費用について語られるとき、しばしば「最低日常生活費」や「ゆとりある老後費」などと耳にしますよね。「わが家は質素に暮らすからゆとりまで考えてなくていい」とお考えの方もいるでしょう。この「ゆとり」の中身は何でしょうか。
ゆとりの上乗せ部分である平均14.0万円の詳細と、あわせて65歳以上の収支を確認しましょう。
ゆとりの上乗せ部分「平均14.0万円」その内訳は?
同調査より、上乗せ額の使途を見ていきます。
老後のゆとりのための上乗せ額の使途(複数回答)
- 旅行やレジャー:60.7%
- 趣味や教養:51.1%
- 日常生活費の充実:49.6%
- 身内とのつきあい:48.8%
- 耐久消費財の買い替え:30.0%
- 子どもや孫への資金援助:22.4%
- 隣人や友人との付き合い:15.5%
- とりあえず貯蓄:3.7%
- その他:0.4%
- わからない:0.4%
※出典:<生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/令和元年度>
それぞれの項目を見ると、旅行やレジャー、趣味や教養といった老後の楽しみとなる部分が多くを占めます。
実際には国内旅行か海外旅行か、行くなら年に何回行くかといった個人差はあるでしょう。
また、身内や隣人、友人との付き合いも含まれています。身近な人との付き合いでも、お土産や食事、旅行など何かと費用はかかりますよね。お孫さんがいるとお年玉や入学のお祝いなどの費用もかかるでしょう。
耐久消費財とは、長期間使用できる日常生活用品で、たとえばテレビや自動車、家具などのこと。老後になり使わなくなるものもある一方で、なくては生活できないものもあるでしょう。
このようにくわしく確認すると、私たちが想像していた「ゆとり」とは少し異なるかもしれません。
楽しみや生きがいとして続けたいこと、生活に必要なものなども含まれるでしょう。
65歳以上の二人以上&単身世帯の収支はいくらか?
では、実際に65歳以上の生活の収支はどれくらいが平均でしょうか。
総務省統計局の「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)」より、二人以上世帯と単身世帯に分けて確認します。
65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)
実収入:25万6660円
支出合計:25万5550円
(支出内訳)
- 非消費支出計(税金や社会保険料):3万1160円
- 消費支出:22万4390円
二人以上世帯の支出の合計は25万円5550円。
先ほどの最低日常生活費の22.1万円を超えましたが、ゆとりある老後生活費よりおよそ10万円少ない結果となりました。
これ以上のゆとりを求めると月々の収入からは難しいため、まとまった貯蓄が必要です。
単身世帯の収支も確認してみましょう。
65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)
実収入:13万6964円
支出合計:14万4687円
(支出内訳)
- 非消費支出計(税金や社会保険料):1万1541円
- 消費支出:13万3146円
単身世帯の支出は14万円台です。しかし収入と比べると7723円の赤字なので、貯蓄から取り崩す必要があるでしょう。
先ほどの「ゆとり」の部分も、各家庭によって求める水準が異なります。
しかし二人以上世帯・単身世帯ともに、収入を見るとゆとりある老後生活費のためにはまとまった貯蓄が必要でしょう。
皆様のご家庭の「ゆとりある老後生活費」のための準備を
老後資金に柱となるのは、年金と貯蓄です。
老後毎月いくらで生活できるのか、年金以外に月いくら貯蓄から取り崩す必要があるかは、早めに知っておきたいところ。
年金生活のおよその収支を把握した上で、私的年金や貯蓄などで老後資金の準備をしたいですね。
「わが家のゆとり」についても、早めに考えてみてはいかがでしょうか。
旅行は年に何回行くのか、趣味にどれくらいお金をかけるのか、子どもや孫との付き合いや資金援助は何をいくらまで出すのかなど。
ある程度決めておかないと、気づいたら貯蓄が残り少しなんて場合もあります。
人生100年時代では、老後だけでも35年間。急な医療費や介護費用、リフォーム費用などがかかる場合もあるでしょう。
2022年、大切な老後資金の準備について、また資産寿命を伸ばす方法についても、時間に余裕のある時に検討されてみてはいかがでしょうか。
昨年の年末調整を間違えてしまったら??
お世話になります。
中西です。改めて本年もどうぞ宜しくお願いします。
今回は年末調整の再提出についてです。
ご存じの通り年末調整は、配偶者控除や基礎控除などの確認と合わせ、該当する人は保険料控除や住宅ローン控除などの内容を記入して提出します。
もし、この年末調整の内容を間違えたまま提出してしまった場合についてご案内します。
良ければ参考になさってください。
まず訂正できるかどうか?
答えはYES
年末調整は提出した後に訂正することができます。
しかし、訂正できる期限が存在するのも事実です。
会社がまだ税務署に提出していない場合
会社は従業員から集めた年末調整の資料を基に、最終的な所得税額を決定し、必要に応じて12月の給与支払いにて還付もしくは徴収を行います。
最終的な所得税額がこれまで毎月徴収していた所得税額よりも多かった場合は還付しますし、逆に少なかった場合は、差額を徴収します。
そして、会社は最終的な「給与の源泉徴収票」および「給与の法定調書合計表」を税務署に1月31日までに提出する必要があります。
そのため、会社がまだ税務署に書類を提出していない場合は、間違えて提出した年末調整の内容を修正できる可能性があります。
会社が税務署に書類を提出した後の場合
会社が税務署に書類を提出した後の場合は、会社では年末調整の内容を訂正することはできません。したがって、従業員自らが確定申告によって行う必要があります。
確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までですので、その間に税務署に申告するようにしましょう。
もし、納税する所得税額がある場合は、申告期間内に合わせて納税する必要があります。
会社が決めた期日に従う
いくら会社が税務署に提出する期日が1月31日までだとはいえ、会社側としても取りまとめる作業が必要です。そのため、会社独自の期限を設けている可能性があります。1月31日よりもまえだから修正可能と思いこまず、まず担当部署の人に年末調整の内容を間違えて提出した旨を伝えたうえで指示を仰ぐようにしてください。
場合によっては、1月中旬でも会社としての期限が過ぎており、確定申告での修正を求められるかもしれません。
年末調整の訂正ってどうやるの?
会社に提出する前、もしくは会社が税務署に書類を提出する前なら、年末調整の訂正は可能です。
年末調整の訂正は、間違った箇所に二重線を引き、その近くの空白部分に正しい内容を記載します。訂正印は不要です。
以前は訂正印の押印が必要でしたが、年末調整の書類自体に押印が不要になってからは、訂正印の押印も不要としています。ただし、会社によっては訂正印の押印を求めるところもありますので、その際は指示に従うようにしましょう。
年末調整の訂正に修正テープや修正液を使用してはだめ?
年末調整の書類の訂正は必ず二重線で行わなければなりません。
修正テープや修正液の使用は認められていません。
また、二重線で訂正する部分があまりに多かったり、修正テープや修正液を使用してしまった場合は、新しく用紙をもらい、全て書き直すことをおすすめします。
年末調整の修正が必ず必要になるケースとは?
年末調整の書類の中には、翌年の扶養控除等(異動)申告書があります。
提出時には控除対象となる扶養家族の情報を記入しますが、その後翌年の12月31日までの間にその内容に変更があった場合は修正して提出する必要があります。
また、年末調整の書類を提出した後に保険に加入したり、配偶者の所得が変わり、控除対象外となったなどのケースでは、修正が必要になります。
年末調整の修正で確定申告が必要になるケース
年末調整の内容を間違えたまま提出してしまい、会社が税務署に提出する期日を過ぎてしまったからといって、全ての人に確定申告が必要になるわけではありません。
確定申告が必要になるのは、訂正された年末調整によって所得税額の還付もしくは徴収が発生する人のみです。
たとえば、配偶者控除の適用範囲内での配偶者の所得見積額を間違えたなど、所得税額の計算に影響のない間違いであれば、確定申告は必要ありません。
年末調整の内容を間違えたまま提出してしまったことにより、確定申告が必要かどうかの判断が自分ではわからない場合は、会社の担当部署の人に確認してみましょう。
還付だけなら早めの確定申告が可能
年末調整の内容を間違えて提出し、最終的に確定申告が必要になった場合でも、所得税額を納税するのではなく、還付を受けるだけなら、翌年の1月から還付申告を受け付けていますので、2月16日よりも前に税務署に提出することができます。
そうすることで、混雑する前に提出できますし、還付金も早く振り込まれます。
還付申告だけということが分かった場合は、できるだけ1月中に申告を済ませてしまうのが良いかもしれませんね。
本年も皆様にとって素敵な1年となるようバリエーション豊かなセミナーを企画しています。
ご都合良ければ是非お待ちしております!
長寿国日本!資産寿命も延ばせたら・・
いつもありがとうございます!
早いもので今年も残り10日程となりました。
皆さんはどのような2021年でしたでしょうか?
今回は来年には是非考えて頂きたい日本の高齢化と資産寿命についてです。
ご存知の通り、日本は世界の中でも長寿国といわれています。
厚生労働省による簡易生命表をみると、平均寿命は女性87.74歳・男性81.64歳と過去最高を記録しています。
総務省統計局「人口統計資料集(平均寿命が高い国)」を参照にすると、1950~55年の日本では平均寿命が女性64.61歳・男性61.00歳でした。今後の2050~55年では女性91.64歳・男性85.45歳、2095年~100年では女性96.63歳・男性90.45歳まで引き上がります。
「人生100年時代」が、もうそこまで迫っている状況です。
この寿命の伸びと反比例して減っていくのが資産です。
老後生活真っ只中の今の70代を参考に、資産寿命を伸ばすヒントになればと思い書かせて頂きます。
現状把握①
~70代の年金額は?~
まずは70代の年金額を確認してみましょう。
資料は厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和元年度)」参照
70代平均年金月額【国民年金】
- 70歳:5万6947円
- 71歳:5万6902円
- 72歳:5万6716円
- 73歳:5万6522円
- 74歳:5万6085円
- 75歳:5万6056円
- 76歳:5万5735円
- 77歳:5万5514円
- 78歳:5万5366円
- 79歳:5万7052円
【厚生年金(含む国民年金)】
- 70歳:14万7292円
- 71歳:14万6568円
- 72歳:14万5757円
- 73歳:14万5367円
- 74歳:14万7330円
- 75歳:14万7957円
- 76歳:14万9693円
- 77歳:15万1924円
- 78歳:15万4127円
- 79歳:15万6714円
あわせて、今のシニア世代の国民年金と厚生年金の平均額も確認します。
男女別【国民年金】平均月額
- 男子:5万8866円
- 女子:5万3699円
平均:5万5946円
男女別【厚生年金(含む国民年金)】平均月額
- 男子:16万4770円
- 女子:10万3159円
平均:14万4268円
国民年金は男女であまり差がありません。
一方で、厚生年金の平均と女性の平均を比べると、4万円以上の差があります。
20歳以上60歳未満の方が原則加入する「国民年金」と違い、「厚生年金」は加入月数や収入に応じて受給額が変わります。そのため、厚生年金は男女差や個人差が出やすくなっています。
現状把握②
~70代の貯蓄額は?~
貯蓄額ではどうでしょうか。
総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2020年(令和2年)平均結果-(二人以上の世帯)」を参照
40歳未満
- 貯蓄現在高:708万円
- 負債現在高:1244万円
40~49歳
- 貯蓄現在高:1081万円
- 負債現在高:1231万円
50~59歳
- 貯蓄現在高:1703万円
- 負債現在高:699万円
60~69歳
- 貯蓄現在高:2384万円
- 負債現在高:242万円
70歳以上
貯蓄現在高:2259万円
負債現在高:86万円
70歳以上の世帯は、純貯蓄額(=貯蓄現在高-負債残高)が最も多い世代となっています。
では、純貯蓄額が2000万円以上あれば、老後は安心なんでしょうか?
70代の老後資金を試算!
実際に、70代の老後資金を試算してみましょう。
女性の平均寿命が87歳のため、老後資金は90歳までの資金とします。夫婦の年金収入は、国民年金平均月額(妻)と厚生年金平均月額(夫)を参考にします。
支出については、ゆとりある老後生活費平均36万1000円(生命保険文化センタ-調べ)を活用します。
ともに70歳の夫婦を仮定
- 夫婦年金:妻5万3699円+夫16万4770円=21万8469円
- 月間支出:36万1000円
- 期間:20年(=90歳-70歳)
- 貯金現在残高:2259万円
- 負債現在残高:86万円
(計算式)
{(21万8469円-36万1000円)×12ヶ月×20年}+(2259万円-86万円)
=▲1247万円
ゆとりある生活を送るためには、さらに1300万円弱が必要です。また、70代後半から介護費用も念頭にいれる必要があるでしょう。
寿命ともに資産寿命を伸ばすコツ
平均寿命が延びても、安心した老後生活を送るためにはお金が必要です。
そのためには、「お金の寿命を伸ばす=資産寿命を伸ばす」ことが重要になってきます。
資産寿命を伸ばすコツは「複利と長期積立」です。
「複利」とは、「利息に利息をつける」方法で雪だるま式に増えていくイメージです。
かのアインシュタインも、人類最大の発明と認めるほどの手法です。
仮に2000万円の資産をつくる場合について、6%を例にあげます。
- 毎月2万円・期間30年:元本720万円→1959万円(元本対比272%)
- 毎月4.4万円・期間20年:元本1056万円→2005万円(元本対比189%)
- 毎月12.3万円・期間10年:元本1476万円→2008万円(元本対比136%)
※前提条件:6%複利、Ke!san「積立計算(複利毎課税)」を活用し試算(※税金は考慮せず)
同じ2000万円をつくるにしても、期間が長いほど少ない金額で大きく増やすことができます。
つまり、「資産を大きく増やしたい→複利を活用する→長い期間を運用する→早く始める」となり、老後生活までにいかに期間を長く取れるのかがカギとなります。
早くはじめるほど、資産もふくらむでしょう。
資産運用を始めようと思っても、「何から始めたらいいのか・ちゃんと続けられるのか」など不安に思われるかもしれません。
そのため、まずはオンラインセミナー等を参考にして、情報収集からはじめてはいかがでしょうか。
ご都合宜しければ弊社各種セミナーご利用なさってください
貯蓄0!?60代の18.3% 将来を考える
60代といえば、定年後のスタートとなる時期です。
現役時と比べ収入は減少し、節約生活へ突入といったこともあるでしょう。
またご自身のセカンドライフを考えなければならない中で、「老老介護」といった問題に直面する可能性もあります。
これからの老後生活資金に加え介護費や医療費など準備していかなければならない中で、資金不足による老後破産をどう避ければいいのでしょうか。
またどのくらいの資産があれば安心できるのでしょうか。
60代の懐事情(資産編)
まず60代の懐事情を参考に見ていきましょう。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和2年)」を参考にします。
60歳代金融資産保有額
- 平均:1745万円
- 中央値:875万円
※平均値は超富裕層の資産額の影響を受けてしまうので、中央値の方が実態に近いでしょう。
- 金融資産非保有者:18.3%
- 100万円未満:3.5%
- 100~200万円未満:4.0%
- 200~300万円未満:4.0%
- 300~400万円未満:3.3%
- 400~500万円未満:4.0%
- 500~700万円未満:5.3%
- 700~1000万円未満:7.5%
- 1000~1500万円未満:7.5%
- 1500~2000万円未満:6.3%
- 2000~3000万円未満:13.3%
- 3000万円以上:19.6%
- 無回答:3.3%
老後資金が将来2000万円不足するといった「老後2000万円問題」がありましたが、2000万円以上の保有割合は32.9%となります。一方で、貯蓄ゼロを示す「金融資産非保有者」の割合は18.3%と約2割に上ります。
60代の懐事情(収入編)
資産の次は収入をみていきましょう。
年金収入をベースとしてみます。
2020年12月公表の厚生労働省年金局「令和元年度厚生年金・国民年金事業の概況」(参考資料3・4)から、国民年金や厚生年金(含む国民年金)を確認してみましょう。
国民年金 男女別年金月額
- 男子:5万8866円
- 女子:5万3699円
全体の平均年金月額:5万5946円
厚生年金保険(含む国民年金)男女別年金月額
男子:16万4770円
女子:10万3159円
全体の平均年金月額:14万4268円
男女の国民年金と厚生年金(含む国民年金)を見てきましたが、それを参考に夫婦の年金月額がいくらになるのかを見ていきましょう。
夫婦の年金月額
- 自営業(夫)と専業主婦(妻):11万2565円
- 会社員(夫)と会社員(妻):26万7929円
- 会社員(夫)と専業主婦(妻):21万8469円
- 専業主夫(夫)と会社員(妻):16万2025円
「自営業(夫)と専業主婦(妻)」と「会社員(夫)」と会社員(妻)」を比較すると、15万5364円となり、年間約186万円の差になります。さらに20年では3728万円、30年では5593万円程度の差になります。
「自営業(夫)と専業主婦(妻)」については厚生年金がない分、自身で資産を築く自助努力が一層必要になります。
老後破産を避けるために。目安の額は?
資産と収支を見てきましたが、老後破産を避けるためにどのくらいの資産額があれば良いのでしょうか。
金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」の「老後2000万円問題」にありました生活費と年数を参考に試算したいと思います。
不足額(必要額)=金融資産-{(収入-生活費)×12ヶ月×年数(老後)+介護費用等}
例えば先程の例の「自営業(夫)と専業主婦(妻)」のパターンで見ると、
不足額(必要額)
=金融資産-{(11万2565円-26万3718円)×12ヶ月×30年+介護費用}
=金融資産-{5441万5080円+介護費用}
一人あたりの介護費用については、生命保険文化センターによると、
介護費用=69万円(一時費用)+7万8000円(月額)×54.5ヶ月=494万1000円
以上を踏まえ、夫婦の介護費用(494万1000円×2)まで換算すると、目安の資産額は約6500万円の資産が必要となります。
老後にいくら必要になるかを考える
老後の資産をどのように築いていけばいいのでしょうか。
ポイントは3つです。
- 資産運用
- 複利
- 長期積立
金融庁のシミュレーションを活用してみると、下記のような試算ができます。
<年利6%で30年間資産運用(複利)した場合>
- 毎月2万円積立の場合:2009万301円
- 毎月6万円積立の場合:6027万903円
毎月コツコツと複利運用をしていけば将来大きな資産を築くことができます。とはいえ資産運用にはリスクが伴うのも事実です。まずは資産運用を考える前に、ご自身のライフプランを見直すとよいかと思います。
そのうえで、老後を含めて今後いくら必要かを検討する時間を設けることが大切になってくるのではないかと思います。
ご興味ありましたら、ご相談お待ちしております。
2040年までに 介護スタッフが280万人必要!?
お世話になります。
厚生労働省で今年、介護サービス見込み量等に基づく介護職員の必要数を公表しました。
それによると、2040年度には約280万人の介護職員が必要となることがわかりました。
そこで今回はこの内容を詳しくみていこうと思います。
介護職員 70万人弱の増員が必要
今回の推計は、「第8期(2021年~2024年)介護保険事業計画」の介護サービス見込み量等にもとづき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計したもの。
それによると、今後必要な介護職員の数は下記の通りとなりました。
- 2023年度…約233万人(+約22万人)
- 2025年度…約243万人(+約32万人)
- 2040年度…約280万人(+約69万人)
※()内は2019年度(211万人)との比較
政府としては、介護職員の処遇改善や離職防止、外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組むとしています。
それでは、介護職員の処遇改善をめぐる状況について、解説していきます。
月額7.5万円の改善も 他職種より低い傾向に
厚生労働省によると、介護職員の処遇改善の実績は下記の通りです。
- 月額平均2.4万円の改善(2009年度~)
- 月額平均0.6万円の改善(2012年度~)
- 月額平均1.3万円の改善(2015年度~)
- 月額平均1.4万円の改善(2017年度~)
- 月額平均1.8万円の改善(2019年度~)
合計:月額平均7.5万円の改善
一方で、他の産業との比較もみてみます。
【平均給与額】介護職員は他職種と⽐較して低い傾向に
それでは、他の職種との給与差について、厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」からみていきます。
介護職員の平均給与は31万5850円で、1年前より1.5万円ほど増加しています。
ただ、看護職員などと比べると少ない傾向にあることがわかります。
介護職員は今後増えるか?
今回は、介護職員が2040年まで約69万人が不足することや、直近の介護職員の給与についてお伝えしました。
介護職員の給与は少しずつ改善されているようですが、他の職種と比べると高い水準であるとは言えないことがわかります。
急速に高齢化が進む中、介護職は社会保障を支える大切な仕事です。
給与の改善はもちろん、介護という仕事をより魅力的に発信する必要性もありそうですね。