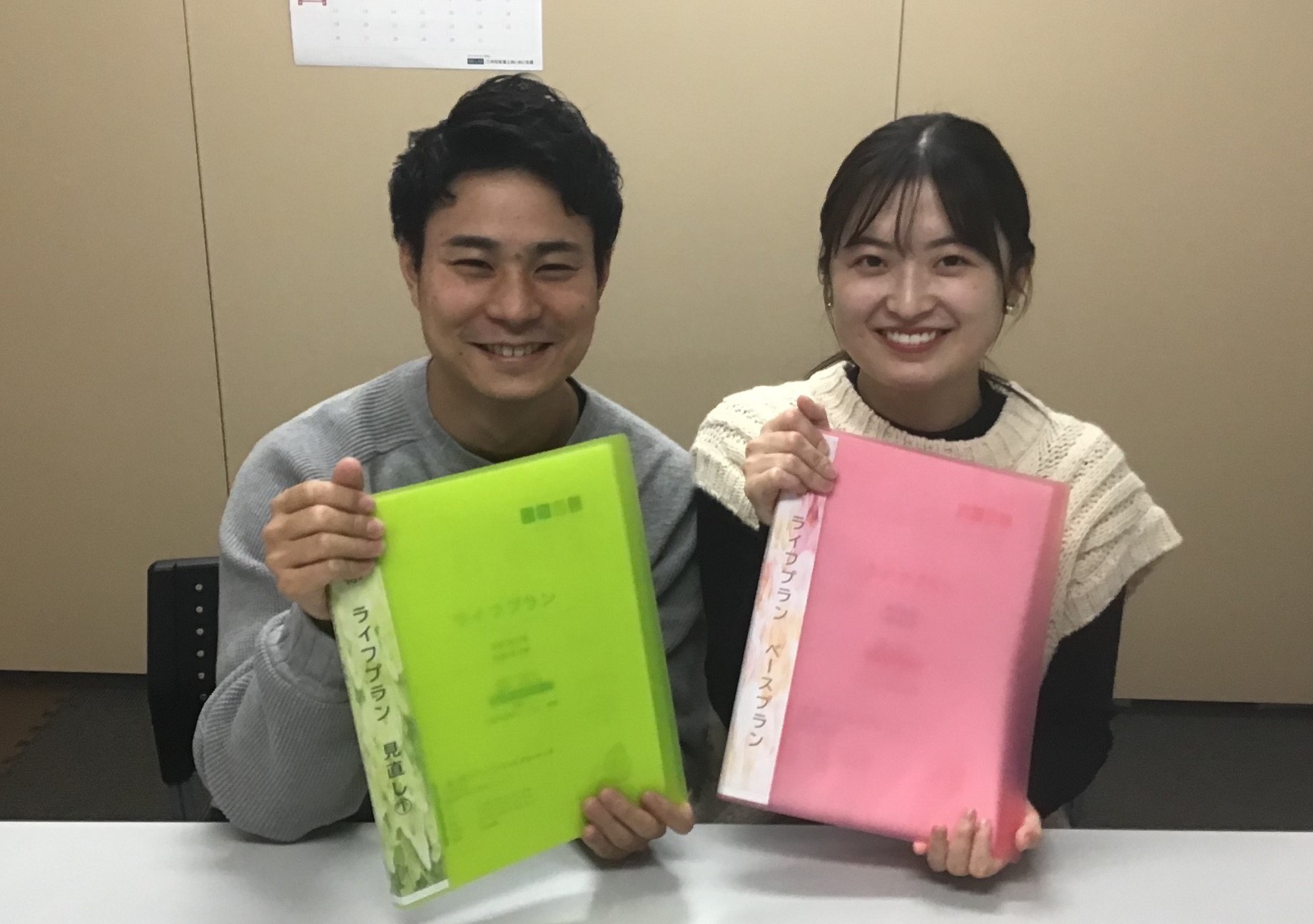Author Archive
明けましておめでとうございます!
明けましておめでとうございます。濱尾です。
本年もよろしくお願いいたします!
弊社の今年の抱負、全体の見通しをお話してみたいと思います。
【今年のスローガン】
「コロナの影響が残る中で、次の時代の動向・流れを見据えて準備を行い、
さらに次の年に向けて成長していく一年としよう!」
【今年・今後の見通し】
2022年「壬寅(みずのえとら):新しく立ち上がること、生まれたものが成長すること」
という意味を持つ年。
2023年、江戸幕府が出来た年から420年目を迎える大きな転換点を迎える節目の年だそう、
その前年、大きな変革に備えて準備をしっかり行い成長していく年としたい。
「心の時代」へ:コロナで疲弊した現在、心の癒しが求められることになる。
また、実態がないものが資産として価値を持つ時代となってくるであろう。
お客様の心・気持ちに寄り添い、癒しを提供していくことがより必要となってくる
時代となってくるのではないか。
コロナと共存しながらの生活・経済の回復を探ることになりそうである。
年始早々のオミクロン株感染者拡大がどう影響してくるのか?
2月北京冬季オリンピックはどうなるのかが気になる。
キーワードとして、脱コロナ経済回復、脱炭素(カーボンニュートラル)、
メタバース(実態がないものが資産として価値を持つ)、
フェムテック(女性の抱える問題をテクノロジーで解決)
が時代の流れとしてどのように社会が変わり、対応していくのか?
国内においては、少子化・低成長経済の閉塞感から脱却出来るのか?
世界との成長の差、拡大が懸念される。
また65歳以上の人がいる世帯割合は全世帯の49.9%約5割、
単独世帯28.8%約3割(内閣府:令和3年高齢社会白書)と
超高齢化、おひとり様増加をたどる社会的背景が抱える課題が
さらにクローズアップされる。
資産防衛(資産凍結)対策、生活維持防衛(見守り・死後対策)対策が必要となる。
今年5月のiDeCo加入年齢拡大、2024年、NISA制度改正に向けた
国・金融庁の「貯蓄から投資」の定着により、
資産形成ムードはさらに拡大していくであろう。
運用の環境では米国を始め諸外国の物価上昇、インフレ懸念から
金利引き上げ政策が株式などのマーケットへどう影響していくかが注目すべき点である。
保険では今年4月の外貨の標準利率引き下げの影響が気になる、
3月までが契約の駆け込み需要となりそうである。
また変額保険の取り組みが、マーケット競争拡大、時代ニーズとして
資産形成と保障の確保をどうするかといった観点から求められると思われる。
(保険は保険会社が運用(内外債券中心)するものから、
自分自身で運用(投資信託)するものという考え方の変化)
以上のような背景から、消費者は多面的な課題・不安を抱え、
今年は昨年以上にFPがライフプランニングが求められる年となるであろう。
弊社として、今まで蓄積してきた事、ノウハウをさらにレベルアップさせて
皆で役割分担、共存していくためにチームプレーも意識して、
新たなことにもチャレンジして、行動・実践を通じて
それぞれが成長して行く年としていきたいと思います!
弊社Vision:「地域貢献度No.1のFP会社」を目指して!!
本年も何卒よろしくお願いいたします。
代表取締役 濱尾壽一
謹賀新年 2022

あけましておめでとうございます
旧年中は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございました。
弊社は本年も、皆様により一層ご満足いただけるファイナンシャルプランナー事務所をめざします。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
なお、新年は5日午後より営業いたしております。
皆様のご健勝とご多幸心よりお祈り申し上げます。
令和4年 元旦
年末年始の休業日について
今年も残すところ、あと3日となりました。
皆様には、ご愛顧を賜りましたことに深くお礼を申し上げます。
本日より弊社、年末休業とさせて頂きます。
来年もより良いサービス向上を図り誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
なお、新年は1月5日(水)午前9時より、平常通り営業させて頂きます。
来年もどうぞよろしくお願いします。
※上記期間中はメール・ホームページ・FAXからのお問い合わせの受付はいたします。
※対応は1月5日以降となりますので、予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げて、年末のご挨拶とさせて頂きます。
長寿国日本!資産寿命も延ばせたら・・
いつもありがとうございます!
早いもので今年も残り10日程となりました。
皆さんはどのような2021年でしたでしょうか?
今回は来年には是非考えて頂きたい日本の高齢化と資産寿命についてです。
ご存知の通り、日本は世界の中でも長寿国といわれています。
厚生労働省による簡易生命表をみると、平均寿命は女性87.74歳・男性81.64歳と過去最高を記録しています。
総務省統計局「人口統計資料集(平均寿命が高い国)」を参照にすると、1950~55年の日本では平均寿命が女性64.61歳・男性61.00歳でした。今後の2050~55年では女性91.64歳・男性85.45歳、2095年~100年では女性96.63歳・男性90.45歳まで引き上がります。
「人生100年時代」が、もうそこまで迫っている状況です。
この寿命の伸びと反比例して減っていくのが資産です。
老後生活真っ只中の今の70代を参考に、資産寿命を伸ばすヒントになればと思い書かせて頂きます。
現状把握①
~70代の年金額は?~
まずは70代の年金額を確認してみましょう。
資料は厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和元年度)」参照
70代平均年金月額【国民年金】
- 70歳:5万6947円
- 71歳:5万6902円
- 72歳:5万6716円
- 73歳:5万6522円
- 74歳:5万6085円
- 75歳:5万6056円
- 76歳:5万5735円
- 77歳:5万5514円
- 78歳:5万5366円
- 79歳:5万7052円
【厚生年金(含む国民年金)】
- 70歳:14万7292円
- 71歳:14万6568円
- 72歳:14万5757円
- 73歳:14万5367円
- 74歳:14万7330円
- 75歳:14万7957円
- 76歳:14万9693円
- 77歳:15万1924円
- 78歳:15万4127円
- 79歳:15万6714円
あわせて、今のシニア世代の国民年金と厚生年金の平均額も確認します。
男女別【国民年金】平均月額
- 男子:5万8866円
- 女子:5万3699円
平均:5万5946円
男女別【厚生年金(含む国民年金)】平均月額
- 男子:16万4770円
- 女子:10万3159円
平均:14万4268円
国民年金は男女であまり差がありません。
一方で、厚生年金の平均と女性の平均を比べると、4万円以上の差があります。
20歳以上60歳未満の方が原則加入する「国民年金」と違い、「厚生年金」は加入月数や収入に応じて受給額が変わります。そのため、厚生年金は男女差や個人差が出やすくなっています。
現状把握②
~70代の貯蓄額は?~
貯蓄額ではどうでしょうか。
総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2020年(令和2年)平均結果-(二人以上の世帯)」を参照
40歳未満
- 貯蓄現在高:708万円
- 負債現在高:1244万円
40~49歳
- 貯蓄現在高:1081万円
- 負債現在高:1231万円
50~59歳
- 貯蓄現在高:1703万円
- 負債現在高:699万円
60~69歳
- 貯蓄現在高:2384万円
- 負債現在高:242万円
70歳以上
貯蓄現在高:2259万円
負債現在高:86万円
70歳以上の世帯は、純貯蓄額(=貯蓄現在高-負債残高)が最も多い世代となっています。
では、純貯蓄額が2000万円以上あれば、老後は安心なんでしょうか?
70代の老後資金を試算!
実際に、70代の老後資金を試算してみましょう。
女性の平均寿命が87歳のため、老後資金は90歳までの資金とします。夫婦の年金収入は、国民年金平均月額(妻)と厚生年金平均月額(夫)を参考にします。
支出については、ゆとりある老後生活費平均36万1000円(生命保険文化センタ-調べ)を活用します。
ともに70歳の夫婦を仮定
- 夫婦年金:妻5万3699円+夫16万4770円=21万8469円
- 月間支出:36万1000円
- 期間:20年(=90歳-70歳)
- 貯金現在残高:2259万円
- 負債現在残高:86万円
(計算式)
{(21万8469円-36万1000円)×12ヶ月×20年}+(2259万円-86万円)
=▲1247万円
ゆとりある生活を送るためには、さらに1300万円弱が必要です。また、70代後半から介護費用も念頭にいれる必要があるでしょう。
寿命ともに資産寿命を伸ばすコツ
平均寿命が延びても、安心した老後生活を送るためにはお金が必要です。
そのためには、「お金の寿命を伸ばす=資産寿命を伸ばす」ことが重要になってきます。
資産寿命を伸ばすコツは「複利と長期積立」です。
「複利」とは、「利息に利息をつける」方法で雪だるま式に増えていくイメージです。
かのアインシュタインも、人類最大の発明と認めるほどの手法です。
仮に2000万円の資産をつくる場合について、6%を例にあげます。
- 毎月2万円・期間30年:元本720万円→1959万円(元本対比272%)
- 毎月4.4万円・期間20年:元本1056万円→2005万円(元本対比189%)
- 毎月12.3万円・期間10年:元本1476万円→2008万円(元本対比136%)
※前提条件:6%複利、Ke!san「積立計算(複利毎課税)」を活用し試算(※税金は考慮せず)
同じ2000万円をつくるにしても、期間が長いほど少ない金額で大きく増やすことができます。
つまり、「資産を大きく増やしたい→複利を活用する→長い期間を運用する→早く始める」となり、老後生活までにいかに期間を長く取れるのかがカギとなります。
早くはじめるほど、資産もふくらむでしょう。
資産運用を始めようと思っても、「何から始めたらいいのか・ちゃんと続けられるのか」など不安に思われるかもしれません。
そのため、まずはオンラインセミナー等を参考にして、情報収集からはじめてはいかがでしょうか。
ご都合宜しければ弊社各種セミナーご利用なさってください
ライフプラン作成しました!(2021年11月)
~ライフプランを作成することで漠然としていた住宅購入費が決まり、今後の人生を想像することができました~
かねてより住宅購入を考えており、私たちが無理なく購入できる金額がどれくらいか想像できませんでした。
そこで、こちらに相談することにしました。
初めは、住宅購入について相談する予定でしたが、ライフプランの作成ができることを知り、作成をお願いしました。どのタイミングでどの程度お金がかかるのかを想定できたことで、漠然としていた住宅購入費が決まり、今後の人生を想像することができました。
また、イベントを企画したり、今後の楽しみについても考えることができました。
ありがとうございました。
担当FP:杉本博美
変わる!「傷病手当金」2022年1月改定
こんにちは!杉本です。
健康保険制度の給付に「傷病手当金」があります。傷病手当金と名のあるものの中でも、これからご紹介する「傷病手当金」とは給付内容が異なる健康保険等もあります。健康保険等でも扶養されているもの(3号保険者)は「傷病手当金」の対象ではないことがほとんどです。そして、国民健康保険にはそもそも「傷病手当金」はありません。
傷病手当金は病気やけがで休業している間の所得を保障し、職場復帰を支援します。働けなくなった日の4日目から給与の約3分の2に相当する額が支給されます。
現在の傷病手当金は、「支給開始日から数えて1年6ヶ月を超えない期間」で、出勤をしたり休んだりを繰り返すことで「支給を始めた日から起算して1年6ヶ月」という条件に合わず、自身の預貯金を生活費に充てるということがありました。ですが、
2022年1月からは「支給日から1年6ヶ月を通算で1年6ヶ月支給される」ようになります。
この改定で、多くの働く人が助かることは間違いありません。
病気やけがで思うように働けず、仕事を休まざるを得ない時、いくらかでも収入があるのとないのでは大きく違います。
一番最初にお伝えしましたが、傷病手当金があるのは、残念ですがすべての健康保険ではありません。
ですので、自身で闘病生活での目に見えない治療費等や普段通りに働けなくなることでの収入減少に備えておかなければなりません。自身だけでなく、家族も巻き込んで闘病生活が強いられます。健康なうちに民間の保険などで備えておいてください。
杉本でした(^^)/
「積立投資のすすめ その41」マイナンバーと口座紐付け
濱尾です、いよいよ師走、
今年もあっという間の1年でした。
皆様はこの1年間いかがでしたでしょうか?
政府がいよいよ来年2022年から
預貯金口座とマイナンバーを連携させる仕組みを作るようです。
これが実現すればコロナで国民に給付された定額給付金や
この12月に支給される予定の18歳以下のこどもがいる世帯への
10万円相当の給付金の支払い
また、災害時に支払われる給付金の支給が
速やかに支払われるようになりそうですね。
さらに、将来は1つの口座を登録すれば他の銀行口座すべてに
マイナンバーが紐付けられるようになるようです。
これによって、相続が発生した場合に
どの金融機関に口座があったかを確認することが難しい
現在の仕組みが、照会をかければ全ての口座がどこにあるか?
が把握できるようにもなるメリットもありそうです。
ただ一方で、個人情報の漏洩の心配、
国に口座情報を把握されてしまうことへの不安が残るなど
まだまだ普及への多くの障害はありそうです。
国に金融機関の財産状況などが把握されれば
相続での手続きも楽になるでしょうが
申告ミスが許されないことにもなるでしょうから
国民にとっては非常に慎重な判断をされる方も多く
おられることと思います。
マイナンバーへは、健康保険証との紐付け
免許証との紐付けなども進んでいるようですので
この流れは止まらないでしょうね。
世界的にもこのような仕組みが存在するようですから
日本もさらに仕組み作りを進めていくことは
停まらないでしょうね。
さあ今年も残り1か月、
何かとせわしくなる年末ですが
皆様、体調に気を付けて乗りきって参りましょう!
よい年の瀬をお過ごしください。
By:濱尾
厚生年金を月30万貰う人は〇%!?
わたしたちは将来いくら年金がもらえるのでしょうか?
年金額について、なんとなく不安を抱えている方も多いと思います。
ゆとりある老後生活を過ごすためには、年金が大いに超したことはありません。
しかし、年金が多ければそれで安心なのでしょうか?
私の前々職はJAでしたが、当時、年金を多く受け取っている方が大勢いらっしゃいました。
今回は厚生年金を「ひと月30万円以上」受け取っている人の割合についてお話させていただきます。
厚生年金「男女別」みんなはどのくらいもらっているのか
まずは、男女別に厚生年金の受給額を見ていきましょう。
厚生労働年金局「令和元年度厚生年金国民年金事業の概況」より
男子
- ~5万円未満:15万977人
- 5~10万円未満:97万6724人
- 10~15万円未満:261万3866人
- 15~20万円未満:436万9884人
- 20~25万円未満:224万9128人
- 25~30万円未満:28万8776人
- 30万円~:1万7626人
女子
- ~5万円未満:31万5100人
- 5~10万円未満:234万1321人
- 10~15万円未満:218万2510人
- 15~20万円未満:41万2963人
- 20~25万円未満:6万3539人
- 25~30万円未満:4166人
- 30万円~:379人
平均年金月額
- 男子16万4770円
- 女子10万3159円
男女平均額:14万4268円
厚生年金を「ひと月30万円以上」受け取っている人の割合は、男子の場合0.17%、女子の場合0.007%、総数0.11%でした。
つまり、30万円以上受け取れるのは、ほんの一握りですね。
では、老後は月々いくらくらい生活費がかかり、どのくらいの金額が毎月不足するのでしょうか。
老後の生活費はいくらかかるか?
みなさんは一昨年話題となった「老後2000万円問題」をご存知でしょうか?
この問題を紐とき、老後生活費が実際不足するかどうかを見ていきましょう。
まず、金融審議会「市場ワーキンググループ」(第21回)厚生労働省提出資料から該当部分を説明すると↓

これが2000万問題の根拠です。
ただし、ここで注意したいことが3つあります。
- 介護費用が含まれていない
- 住居費が1万3656円で計算されている
- 収入と支出は人それぞれ
現在85歳以上で介護認定を受ける人の割合は、59.3%と非常に多くなっています。(生命保険文化センター調べ)
また、入居時費用のある有料老人ホームに5年間入居した場合は、岡山県の相場試算で900万円以上が必要です。(LIFULL介護調べ)
長生きリスクを考えると、介護費用は備えておいたほうが良さそうですね。
さらに、賃貸派の方は老後の生活費の中に家賃も含める必要があるでしょう。
東京都の家賃相場は約8万円(ハウスコム調べ)ですので、その金額を毎月支出に加算する必要がありそうです。
なお、ご自身がどのような老後生活を送りたいかによっても、必要な金額は変わります。
上記のモデルケースは、「必要最低限の老後生活費」基準です。
公益財団法人生命保険文化センターのデータによると、ゆとりある老後を暮らしたい場合は、月々生活費が36.1万円必要という調査結果があります。
つまり、多くの方は2000万円だけでは足りないことになるでしょう。
老後対策で抑えたい、【長期でコツコツ】
それでは、足りない資金をどのように準備していけばよいでしょうか。ポイントがいくつかあります。
銀行金利(0.001%)で資産を倍にしようとすると、気の遠くなるほどの時間がかかります。
一方、例えば6%の運用ができた場合、より早く資産を倍に増やせます。
運用する際に大切なのが、「長期でコツコツ運用」していくことです。
金融商品は日々値動きがあります。運任せに一括で大きな資金を投資してしまうと、タイミングによっては大きな損失を被ってしまいます。
しかし、長期間毎月積立てしていくことで、そのリスクを下げることができます。
しかし、長期積み立てをしていく前提として、健康で働き続ける必要があります。
投資を続けるためには、コツコツ長期積立運用をしていく際の一番のリスクを回避することが大切になってきます。
具体的には、病気や大怪我で、介護状態になり給与を受け取れなくなった場合や給与が下がるケースを避けることです。
そのような長期で積立していく際のリスクは、保障でカバーしておきましょう。
これからの時代は、自助努力で老後資金を準備する時代になりそうですね。
その際に、何から始めればよいかわからない方も多いと思います。
情報収集も勿論大事ですが、まずは相談から始めてみませんか?
お気軽にお問合せください
インフルエンザが怖くなる季節
こんにちは!杉本です。
ワクチン接種が普及したおかげか、全国的にコロナが段々と落ち着いてきています。
しかし、これから寒さも激しくなっていきますので、今度はインフルエンザが気になってきます。
インフルエンザはしっかりと病院で診察してもらい、処方箋を頂きご自宅で療養すると治る病気です。
しかしそんなインフルエンザも昔は死亡のリスクが高かった事をご存じでしょうか?
世界史でも有名なスペイン風邪はインフルエンザが原因と言われています。
全世界で感染者約6億人、死者2000~4000万人も出したパンデミックの一つです。
今では医学が進歩しインフルエンザで死亡するケースは稀ですが、それでも年間3000人程は日本でも死者が出ています。
コロナも落ち着いてきてはいますが、完全に感染者が0になる事は難しく、今後もコロナが原因の死亡リスクや長期入院は付きまとってくる可能性は十分にあります。
それだけでなく、新たな感染症のリスクも捨てきれない所です。
そういったリスクを伴っている世の中で、長期入院による出費や収入の減少はやはり痛手となってくる所になります。
リスク対策の一つとして保険加入があります。
就業不能に対する保険や感染症の特約・保険を多くの保険会社で販売していますが、一体何が違うのか難しい所かと思います。
各保険会社の商品の特徴を公平に判断してくれる人が大事になってきます。
ご自身の保険が現在~将来のリスクに対応している無理の無い保険かどうか?、
一度プロにご相談ください。
岡山ファイナンシャルプランナーズでは保険相談を無料で行っております。
FPという立場から、あなたの収支に合わせた最適なプランを提案いたします。
無理な加入を勧めたりは絶対にいたしません。
保険だけでなく、お金全般の問題の解決ができるのが、独立系FP事務所である「岡山ファイナンシャルプランナーズ」です。是非ご相談ください。
お待ちしております。
杉本でした(^^)/
「積立投資のすすめ その40」 新500円硬貨
こんにちは、濱尾です。
すっかり秋めいてきました、因みに今日は文化の日。
晴天でとても気持ちがいいですね。
先日、11月1日から500円硬貨が新しくなるとニュースで言ってました。
私はまだ実物にお目に掛かってませんが。
また先日、新聞にお金に関する面白いクイズが掲載されていました。
チョット紹介してみます。
2000年に発行が始まった今の500円硬貨に500はいくつある?
①2 ②3 ③4
答えは③
500という文字・数字が裏表で4つある。
皆さん、知ってましたか?
新500円硬貨には計両面で6つになるそうです。
探してみましょう!
重さも0.1グラム増えて7.1グラムになるそうです。
次に、今使える紙幣の種類は?
①9 ②17 ③22
答えは③22種類。
知りませんでした!
1885年から今まで、53種類の紙幣が発行されているそうです。
そのうちの22種類、
1885年発行の1円札や10円札、50円札なども
まだ使用できるとのこと。
次に、東日本大震災の復興事業、記念貨幣で正しいのは?
①小学生が一部デザイン
②最高が10万円
③多色刷りはない
答えは①
そうだったんですね!
2015年にそれぞれ4種類の1万円金貨と千円銀貨が発行された。
デザインが公募され、銀貨の1つに
神奈川県の小学4年生が描いた、
子供が国旗を持って日本を応援する絵が選ばれた。
そうだったんですね!
身近なお金のことですが
色々な工夫や想いがあるんですね。
弊社にて、運用においての資産形成セミナーを実施中!
興味ある方はこちらから見てください。
↓ ↓ ↓
https://peraichi.com/landing_pages/view/assetformation-okayamafp
By:濱尾
« Older Entries Newer Entries »